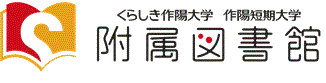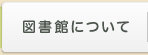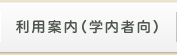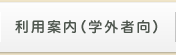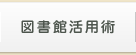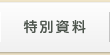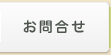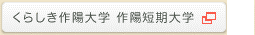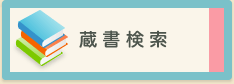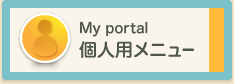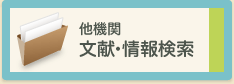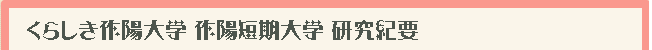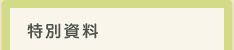あ
| 著者 | 論文 | 巻号 |
|---|---|---|
| 青柳 謙二 | マーラー作曲交響曲第10番演奏会用ヴァージョン作成時の デリック・クックの姿勢 |
40(2) |
| 青柳 謙二 | ドキュメントからみたドビュッシーとサティの関係 | 38(2) |
| 青柳 謙二 | 用語「印象主義」とドビュッシー | 38(1) |
| 青柳 謙二 | 「ドビュッシーとサティの相互影響」 | 37(1) |
| 青柳 謙二 | コルトー版リスト作曲<超絶技巧練習曲集> -「演習版」にみる解釈- |
35(2) |
| 青柳 謙二 | 音楽作品のテクストとしてのゲーテ「ファウスト」 -ボイト作のオペラ<メフィストーフェレ>を例に- |
31(1) |
| 中永征太郎 青山 尚史 片山 湖那 大野婦美子 |
貝原益軒の養生訓にみられる幼育 -「寒冷と三分の飢え」の根拠- |
41(2) |
| 赤木 文男 | <研究ノート> パーソナルコンピュータを利用したストアー内レジ作業 (販売情報の効率的運用と管理に関する研究 第1報) |
22(2) |
| 赤木 文男 | 生産情報の効率的運用と管理に関する研究 (パソコンを使用した生産システムの経済性分析) |
22(1) |
| 赤木 文男 梅田 和子 豊福 泰子 |
<研究ノート>リレーショナル・データベースを使用した秘書 業務の効率化に関する一考察 |
22(1) |
| 赤木 文男 | <研究ノート>生産情報の効率的運用と管理に関する研究 (パソコンを使用した時間情報のリアルタイム処理) |
21(2) |
| 赤木 文男 | 人工知能のための論理的プログラム言語Prolog | 21(1) |
| 赤木 文男 | 生産情報の効率的運用と管理に関する研究 -情報処理にセル構成法を利用した多種製品組立システムの設計とその評価- |
20(2) |
| 赤松 英彦 | <教育研究実績報告> 「音楽総合研究」におけるポピュラー音楽理論の学習と実践 -学習の現場を通して- |
50(1,2) |
| 秋山 博正 | 「道徳」教科化による変更の本質 | 49(2) |
| 秋山 博正 | <意味>としての浄土 | 49(1) |
| 秋山 博正 | 生徒指導と道徳教育が協働育成すべき「豊かな心」 | 48(2) |
| 秋山 博正 | 親鸞系思想における背反・相補関係 | 47(2) |
| 秋山 博正 |
「人間としての在り方生き方に関する教育」の要点 | 46(1) |
| 秋山 博正 大來 尚順 原田 和男 松田 正典 |
メリトクラシーとアミタクラシーの倫理的背反と相補 -人間形成と社会形成の真の在り様の考究- |
45(2) |
| 秋山 博正 |
価値洞察の補完者としての当為 | 45(1) |
| 秋山 博正 |
規範意識を高揚させるものとしての価値洞察 | 44(2) |
| 秋山 博正 |
高等学校での道徳教育への取り組み方 | 43(2) |
| 秋山 博正 |
高等学校における道徳教育の充実 -2009年3月告示「高等学校学習指導要領」を手がかりにして- |
42(2) |
| 秋山 博正 大來 尚順 原田 和男 松田 正典 |
パラダイム・シフトの時代の悲劇を救う世界観 -善導思想と西田哲学についての考察- |
41(2) |
| 秋山 博正 原田 和男 松田 正典 |
文明のダイナミズム -デュアル・カルチャー構造論- |
41(1) |
| 秋山 博正 原田 和男 松田 正典 |
善導のリアリズムの精神とその歴史的展開 | 38(1) |
| 秋山 博正 | 「心の教育」の展開 | 36(2) |
| 秋山 博正 | 親鸞入門-特にその生涯と思想的背景を顧慮して(ドイツ文) | 33(2) |
| 秋山 博正 | 人間と技術との関係論の試み-技術に関する態度- | 33(1) |
| 秋山 博正 | 被教育者としての教師-『道徳教育』のための基本的態度- | 29(2) |
| 秋山 博正 | 平等をめぐる問題-差別に対する実践的態度- | 29(1) |
| 浅野 泰昌 | 保育における絵本の読み聞かせの要点 | 49(2) |
| 麻生 泰弘 | ウェーブレット・ノート(英文) | 33(1) |
| 麻生 泰弘 | Note on Power Sun Function of Positive Integers | 27(1) |
| 麻生 泰弘 | 「ハイパーカード」を用いた情報処理教育の試み | 23(2) |
| 麻生 泰弘 | <資料> dBASEⅢPLUSを用いた図書システムの設計 |
22(1) |
| 足立 正 藤澤 千恵 |
未熟練者における蹴り脚の動作様式に関するラテラリティ | 34(1) |
| 桑田 繁 山地 裕子 坂上 ルミヱ 矢内 直行 足立 正 |
行動論的音楽療法(I):ダウン症女児に対するプレマックの 原理の適用 |
27(1) |
| 桑田 繁 矢内 直行 足立 正 坂上 ルミヱ |
音楽専攻の大学生は本当に外交的か? -モーズレイ性格検査による調査- |
26(2) |
| 足立 正 | 幼児の蹴球動作に関するバイオメカニクス的研究 -動作中における蹴り足の角度・速度変化およびImpact時 の特徴を中心として- |
25(2) |
| 阿部 英雄 | ピアノ演奏における5指練習の基礎 | 25(1) |
| 網中 雅仁 | <研究ノート> 社会福祉協議会の認知度向上に関する提言 |
50(1,2) |
| 網中 雅仁 | 管理栄養士養成課程に学ぶ大学1年生の基礎学力と公衆衛生学分野の習得度との関連性 | 49(2) |
| 網中 雅仁 | 健常者における尿中ポルフィリン濃度の日内変動に関する研究 -遺伝性ポルフィリン症の難病指定による基準値の検討- |
49(1) |
| 安東 敬子 | 舞踊に関する一考察 | 19(1) |
い
| 著者 | 論文 | 巻(号) |
|---|---|---|
| 居川 寛子 | <教育研究実績報告> 幼児教育における鍵盤ハーモニカ指導教材の考察 |
50(1,2) |
| 石川 顕子 藤原 尚子 田淵 満子 山下 静江 |
栄養教諭養成課程における現状と課題 | 43(1) |
| 池田 忠夫 | <活動報告> 情操教育を重視した幼児教育の実践-方策その2- |
17(1) |
| 池田 忠夫 | <活動報告> 情操教育を重視した幼児教育の実践-方策その1- |
15(1) |
| 池田 忠夫 | 情操教育を重視した幼児教育の実践-基礎編- | 14(1) |
| 池田 忠夫 | 幼児期における人間尊重の教育の具体的展開 (部落差別解消の基盤としての) |
13 |
| 池田 忠夫 | 幼児期における人間尊重の教育 | 12(2) |
| 石崎 琢也 | 開発組織と販売組織の相互作用 -産業勃興過程における製品戦略の形成- |
42(2) |
| 石崎 琢也 | 技術優位と競争劣位:技術転換期における企業行動の分析 | 39(1) |
| 磯野 達也 | アスペクト概念と動詞の事象構造 -瞬時性とスケール構造- |
43(1) |
| 磯野 達也 | <研究ノート> 動詞の意味成分について -動能構文再考- |
43(1) |
| 磯野 達也 | Polysemy and Lexical Representation: Intransitive Locative Alternation, Verbs of Motion and Verbs of Emission |
40(2) |
| 磯野 達也 | 英語の動詞が表す「出来事」 | 39(1) |
| 市坡 よし子 | <教育研究実績報告> 小学校教員養成課程における国語科音声言語の教材開発 |
50(1,2) | 斎 求 | ブラームスの「四つの厳粛な歌」演奏までの考察 | 23(2) |
| 出射 栄 | 私の描く新しい粒子的世界-万有科学入門- | 5 |
| 出射 栄 | 化学反応熱の正体 -化学変化の原因(近接説)--順応質量の概念- |
5 |
| 出射 栄 | 量子仮説とそれに関連する種々の現象について(第二報) | 4 |
| 出射 栄 | 量子仮説とそれに関連する種々の現象について(第一報) | 3 |
| 伊藤 智 | 発達障害児の母親の音楽習慣と心理的ストレスおよび子どもの障害受容との関係 | 50(1,2) |
| 内藤 典子 伊藤 智 |
高次脳機能障害者家族の介護負担軽減のための音楽療法の可能性の検討 | 47(1) |
| 妹尾 佳美 頼島 敬 伊藤 智 |
被虐待児に対する音楽療法の可能性 -虐待による心的外傷を中心にした文献検討- |
40(1) |
| 松川 亜沙美 伊藤 智 |
高齢者施設における音楽療法の展望と課題 -チーム医療の参入を見据えて- |
39(2) |
| 廣畑 智恵子 伊藤 智 |
音楽聴取が心身に及ぼす影響について -「3種類の音楽」比較 による- |
39(1) |
| 中本 美紀 伊藤 智 |
健全な親子関係の形成のための音楽習慣の有効性と音楽療法の可能性の検討 | 39(1) |
| 山田 由希子 横内 理恵 伊藤 智 |
幼児を対象にした音楽療法において視覚的刺激が及ぼす影響 について |
38(2) |
| 横内 理恵 伊藤 智 |
ダウン症児に対する音楽を媒体とした治療教育的アプローチに 関する一考察 |
38(1) |
| 伊藤 智 | 脳血管障害を伴ったリハビリテーションでの音楽療法の効果に 関する研究(第1報) |
37(2) |
| 稲岡 達雄 | 外交政策と国民 | 1 |
| 稲谷 靖子 | 図画工作科に関する研究 -曾根靖雅の学習のメトーデ理論と木下竹次の合科自律学習法をもとに- |
49(1) |
| 渡邉 照美 森 楙 山野井 敦徳 詫間 晋平 福井 俊雄 稲谷 靖子 |
大学に期待される子育て支援の内容
-地域のニーズ調査から - |
43(2) |
| 猪原 敬介 上田 紋佳 塩谷 京子 |
幼児期から児童期における読み聞かせ頻度の変改と保護者の持つ 読み聞かせの効果への期待 -小学校に児童を通わせる保護者を対象とした実態調査- |
50(1,2) |
| 山下 静江 井町 和香 武藤 志真子 |
若年女子の身体意識と体脂肪率および栄養摂取量との関係 からみた栄養教育の方向性に関する一考察 |
39(2) |
| 山下 静江 井町 和香 武藤 志真子 |
体脂肪率の季節変動とその性差および地域差 | 38(2) |
| 今西 悦子 | 発育期における必須アミノ酸摂取量の研究 -津山市の学校給食による必須アミノ酸摂取量ー |
12(2) |
| 須藤 浩 今西 悦子 |
卵黄の着色に関する研究(第1報) ニ三市販の着色剤の効果 |
8(1) |
| 今西 一実 | 社会的態度の因子論的研究(Ⅰ) | 5 |
| 今西 一実 | 同調行動に関する実験的研究 | 3 |
| 向後 千里 今村 真未 |
食環境とおいしさのフィッティングイメージ -くらしき作陽大学におけるフードコーディネートの事例より- |
48(1) |
| 守屋 操 井山 房子 古埜 弘子 白神 繁子 平松 由美子 馬場 訓子 高橋 慧 |
幼稚園教育実習の事前指導の在り方を探る -実習前の学生の心情から- |
50(1,2) |
| 長石 啓子 岩井 景子 |
大学生の喫煙実態と出生への影響認識 -4年制大学食文化学部の場合- |
39(1) |
| 小上 和香 桐野 顕子 岩崎 由香里 |
保育者の就労状況及び行動変容の準備性が子どもの食生活に与える影響 | 49(2) |
| 矢内 直行 岩永 誠 前田 圭子 |
印象の異なる音楽が聴き手に及ぼす精神生理学的影響に 関する研究 |
26(2) |
| 岩永 誠 坂上 ルミヱ 矢内 直行 |
テンポの好みに関する実験的研究(V) -音楽を刺激に用いて- |
25(2) |
| 岩永 誠 坂上 ルミヱ 矢内 直行 |
テンポの好みに関する実験的研究(Ⅳ) -刺激の音色の効果- |
25(1) |
| 岩永 誠 坂上 ルミヱ 矢内 直行 |
テンポの好みに関する基礎的研究(Ⅲ) -音楽に関する生理反応の同調現象について- |
24(2) |
| 岩永 誠 坂上 ルミヱ 矢内 直行 |
音楽聴取時の精神生理学反応に関する研究(Ⅱ) -音の大きさとの関係 その2- |
24(1) |
| 岩永 誠 坂上 ルミヱ 矢内 直行 |
テンポの好みに関する基礎的研究(Ⅱ) -音楽に関する生理反応の同調現象について- |
23(2) |
| 矢内 直行 岩永 誠 沈 暁明 |
新しい幼児の音楽教育の試み -ボディシンセサイザーの応用- |
23(1) |
| 岩永 誠 坂上 ルミヱ 矢内 直行 |
音楽聴取時の精神生理学的反応に関する研究(Ⅰ) -音の大きさとの関係- |
23(1) |
| 岩永 誠 坂上 ルミヱ 矢内 直行 |
テンポの好みに関する基礎的研究(Ⅰ) -生理反応とテンポの関連について- |
22(2) |
| 沈 暁明 矢内 直行 岩永 誠 |
<研究ノート>ボディシンセサイザーの提唱 | 22(2) |
| 岩永 誠 | APQ短縮版の標準化の試み | 22(1) |
| 岩永 誠 | 3要因モデルに基づく不安尺度作成の試み | 21(2) |
| 桂 亨 岩原 留美子 |
<資料>食塩摂取量と健康との関係に関する研究(第二報) | 17(1) |
| 岩間 泉 Sutrisno Iwantono |
定着社会における農業発展のメカニズム -ジャワ島農村、農業の分析方法- |
32(2) |
| 岩間 泉 Sutrisno Iwantono |
ジャワ島における近代化を担うジャワ農業・農村の課題と共同 組合の役割 |
31(2) |
う
| 著者 | 論文 | 巻(号) |
|---|---|---|
| 山下 静江 桐野 顕子 内海 亜希子 |
自己管理スキルおよび自己効力感は、個人の食行動に影響する要員となるか | 45(2) |
| 山下 静江 内海 亜希子 桐野 顕子 |
栄養アセスメント能力向上のための効果的な教育介入について考える -食品の目測能力の視点から- |
45(2) |
| 山下 静江 内海 亜希子 武藤 志真子 |
食事調査の自己申告と心理的要因 - 栄養アセスメント能力向上のための効果的な教育介入について考える ー |
44(2) |
| 山下 静江 小上 和香 内海 亜希子 武藤 志真子 |
栄養アセスメント能力向上のための効果的な教育介入について考える - 食事調査の制度の視点から ー |
43(2) |
| 中永征太郎 片山 湖那 大野婦美子 梅島 元子 川口 洋 高木 康治 高木 弘子 額田真喜子 松元 直歳 諸岡 浩子 塩見慎次郎 |
中学生・高校生における不定愁訴の発現からみた生活条件 | 43(1) |
| 梅島 元子 片山 湖那 藤原 郁子 中永征太郎 |
保育園児の起床時刻からみた生活状況について | 42(1) |
| 中永征太郎 片山 湖那 大野婦美子 梅島 元子 川口 洋 高木 弘子 額田真喜子 松元 直歳 諸岡 浩子 塩見慎次郎 |
高校生の生活習慣と不定愁訴の発現・食物摂取頻度・躁うつ傾向との関わり | 42(1) |
| 赤木 文男 梅田 和子 豊福 泰子 |
<研究ノート>
リレーショナル・データベースを使用した秘書 業務の効率化に関する一考察 |
22(1) |
| 須藤 浩 内田 仙二 楠本 恭女 |
卵黄の着色に関する研究(3) 2種の果皮とアルファルファミール添加の効果 |
9(1) |
え
| 著者 | 論文 | 巻(号) |
|---|---|---|
| 遠藤 昌代 | 小学校における発達障害のある児童の教育支援体制に関する研究Ⅰ 通常の学級に在籍する広汎性発達障害のある児童の教育支援体制の試み -校内リソースを活かしたかした小集団指導を通して- |
42(1) |
| 遠藤 マツヱ 新山 睦 長石 啓子 |
離乳食の実態と親子関係に関する研究(第1報) -保育園児の園生活の観察と保護者の離乳食調査- |
36(1) |
| 遠藤 マツヱ | 壮年期におけるボランティア活動の実態に関する研究 -ボランティア活動に対する参加意識の関連構造- |
34(1) |
| 遠藤 マツヱ 梶田 裕美 |
家庭経営における人間関係形成に関する研究 | 33(2) |
| 遠藤 マツヱ | 高齢期における生活経営の枠組みに関する考察 -上海国際高齢者年の会議からみた生活経営上の課題 |
32(2) |
| 遠藤 マツヱ 梶田 裕美 |
家庭経営における人間関係形成に関する研究 -児童・生徒の生活時間にみる親子関係- |
31(2) |
| 遠藤 マツヱ | 壮年期におけるボランティア活動の実態に関する研究 | 31(1) |
お
| 著者 | 論文 | 巻(号) |
|---|---|---|
| 大桐 国光 | 児童画における表現形式の分類 | 3 |
| 大杉 淳子 | <資料>「健康と酒に関する考察」のための基礎資料 | 15(1) |
| 大野 貴司 | アミノ酸代謝異常に伴う疾患 -プロリダーゼ欠損症の臨床と病態- |
43(2) |
| 中永征太郎 片山 湖那 大野婦美子 梅島 元子 川口 洋 高木 康治 高木 弘子 額田真喜子 松元 直歳 諸岡 浩子 塩見慎次郎 |
中学生・高校生における不定愁訴の発現からみた生活条件 | 43(1) |
| 中永征太郎 片山 湖那 大野婦美子 梅島 元子 川口 洋 高木 弘子 額田真喜子 松元 直歳 諸岡 浩子 塩見慎次郎 |
高校生の生活習慣と不定愁訴の発現・食物摂取頻度・躁うつ傾向との関わり | 42(1) |
| 中永征太郎 青山 尚史 片山 湖那 大野婦美子 |
貝原益軒の養生訓にみられる幼育 -「寒冷と三分の飢え」の根拠- |
41(2) |
| 大野婦美子 片山 湖那 中永征太郎 |
中学生における「清涼飲料」の使用頻度と生活習慣との関わり | 41(1) |
| 大野 婦美子 笠井 八重子 |
こんにゃくの力学的特性に及ぼすでんぷん添加の影響 | 38(2) |
| 大野 婦美子 山野 善正 合谷 祥一 笠井 八重子 |
コンニャクゾル及びゲルの微細構造に及ぼす飛粉添加の影響 | 34(2) |
| 大野 婦美子 笠井 八重子 |
平行板方式による精粉「のり」の粘弾性測定手法の検討 | 33(2) |
| 大野 婦美子 笹井 一男 |
柏餅生地の物理的性質について -冷凍生地における解凍の影響- |
29(1) |
| 大野 婦美子 | 柏餅生地の静的粘弾性に及ぼす加水量の影響 | 27(1) |
| 大野 婦美子 | そば全粒粉を用いたパンの調製とその食味 -配合材料の影響- |
26(2) |
| 小西 英子 大野 婦美子 |
食事と貧血との関係に関する研究(第3報) | 16(1) |
| 松田 節子 大野 婦美子 |
<調査報告> 美作地方の食習俗とその変遷について | 10(2) |
| 作詞 大手 拓次 作曲 菅井 邦介 |
男声合唱のための組曲 「みずのほとりの姿」 |
6(1) |
| 大林 秀弥 | 「文化十年久米南条・北条十七ケ村江戸越訴事件」補遺 | 18(1) |
| 大林 秀弥 | 文化十年久米南条・北条十七ケ村江戸越訴事件 第二部 事件の解明 |
14(2) |
| 大林 秀弥 | 「文化十年久米南条、北条十七ヶ村江戸越訴事件」 第一部 原因と経過 |
13 |
| 大林 秀弥 | 維新期岡山県美作地方における地主経営の実態報告(その一) | 9(1) |
| 大林 秀弥 | 明治十年代の美作地方の消費生活 | 6(1) |
| 大林 秀弥 | 美作の林業 | 3 |
| 大林 秀弥 | 低開発諸国人口問題序説 | 2 |
| 大林 秀弥 | 資本の回転と利潤率 | 1 |
| 大林 秀弥 | 年季奉公人について | 1 |
| 大原 荘司 橋本 英夫 |
仏法エキスパートシステムの構築Ⅰ | 22(1) |
| 大原 荘司 長友 正平 |
レーザー誘起マイクロマシーニングシステム | 20(2) |
| 大矢 一人 | 『岡山県軍政部月間活動報告書』の体裁と内容 | 25(2) |
| 大矢 一人 | 岡山県軍政部の人事と機構 | 25(1) |
| 大矢 一人 | (続)岡山進駐と学校視察 | 24(2) |
| 大矢 一人 | 講義形式と発表形式を融合した教授方法に関する一考察 -「幼児教育史」の授業を通じて- |
24(1) |
| 大矢 一人 | 岡山進駐と学校視察 | 23(2) |
| 秋山 博正 大來 尚順 原田 和男 松田 正典 |
メリトクラシーとアミタクラシーの倫理的背反と相補 -人間形成と社会形成の真の在り様の考究- |
45(1) |
| 秋山 博正 大來 尚順 原田 和男 松田 正典 |
パラダイム・シフトの時代の悲劇を救う世界観 -善導思想と西田哲学についての考察- |
41(2) |
| 杉山 貴義 岡井 克明 |
<研究ノート> くらしき作陽大学子ども教育学部学生の体力特定について |
50(1,2) |
| 岡井 克明 | 父子たいそう教室の実施とその効果について -父子のふれあいと子どもの運動能力の開発- |
49(2) |
| 岡田 敬二 | <研究ノート> 環境芸能が奏でる”人と自然の鼓動”について | 31(2) |
| 岡田 敬二 | 作曲作品「水色川と生きよう」 | 31(1) |
| 岡田 扇和 河村 敦 |
食生活習慣がニート傾向に及ぼす影響 | 39(2) |
| 小笠原 幹夫 | パリ万国博のもたらしたもの-栗本鋤雲を中心に- | 34(2) |
| 小笠原 幹夫 | 自由民権運動と芸能・演劇 その四 | 34(1) |
| 小笠原 幹夫 | 自由民権運動と芸能・演劇 その三 | 33(1) |
| 小笠原 幹夫 | 自由民権運動と芸能・演劇 その二 | 32(2) |
| 小笠原 幹夫 | 北村透谷・与謝野鉄幹における政治意識 -『楚因之詩』と『東西南北』をめぐって- |
32(1) |
| 小笠原 幹夫 | 続・幕末の洋楽と明六社啓蒙思想 | 31(1) |
| 小笠原 幹夫 | 幕末の洋学と明六社啓蒙思想 | 30 |
| 小笠原 幹夫 | 自由民権運動と芸能・演劇 その一 | 29(2) |
| 小笠原 幹夫 | 津山藩と洋学-津田真道・箕作麟祥を中心に- | 29(1) |
| 小笠原 幹夫 | 続・東アジアと明治日本-日清戦争とは何だったのか- | 28(2) |
| 小笠原 幹夫 | 東アジアと明治日本-『蹇蹇録』の戦略的思考に学ぶ- | 28(1) |
| 小笠原 幹夫 | 文学における日清戦争の意味 -独歩・一葉・子規のナショナリズムを中心に- |
27(2) |
| 小笠原 幹夫 | 坪内逍遙の政治小説観について | 27(1) |
| 小笠原 幹夫 | 箕作麟祥の仏学-『国政転変ノ論』を中心に- | 26(2) |
| 小笠原 幹夫 | 近松と太平記読み | 26(1) |
| 小笠原 幹夫 | 日本のラ・ヴァンデ-美作血税一揆についての一考察- | 25(2) |
| 小笠原 幹夫 | 近世末期演劇における話芸の影響 | 25(1) |
| 小笠原 幹夫 | 近松と近代作家 | 24(2) |
| 小笠原 幹夫 | 近松の華夷思想-『国姓爺合戦』をめぐって- | 24(1) |
| 小笠原 幹夫 | 西鶴の作品にみる幕藩制と町人意識 | 23(2) |
| 小上 和香 桐野 顕子 岩崎 由香里 |
保育者の就労状況及び行動変容の準備性が子どもの食生活に与える影響 | 49(2) |
| 山下 静江 小上 和香 内海 亜希子 武藤 志真子 |
栄養アセスメント能力向上のための効果的な教育介入について考える - 食事調査の制度の視点から ー |
43(2) |
| 木本 光子 松田 英毅 山下 津真子 草苅 伊佐江 岡本 幸江 多胡 嘉修 |
津山を中心とした吉井川の水質に関する基礎的研究(第1報) | 7(1) |
| 松本 隆行 岡本 浩明 |
情報処理技術に対する意識と情報処理関連科目の履修状況 | 49(2) |
| 小川 長 木戸 啓仁 |
中小企業に対する経済政策の効果 -岡山県内の経営革新計画承認企業を事例として- |
41(2) |
| 金行 孝雄 小川 尚武 |
<研究ノート> ビルベリー抽出物に含まれるデルフィニジン 3-O-β-グルコピラノシドの同定 |
43(1) |
| 岡 弘道 | アートマネジメント教育の理路と実践 | 32(2) |
| 額田 真喜子 小林 孝人 沖野 登美雄 山本 功男 |
新種のInocybe leptodermaの西日本における発生地 (英文) |
33(2) |
| 奥山 尊代 | 「ことばの力」と問いの共有-ある授業実践をめぐって- | 37(2) |
| 奥山 尊代 | <研究ノート>「ことばの力」と対話形成 -ある授業実践を手がかりにして- |
35(2) |
| 奥山 尊代 | 鎌倉アカデミアにおける対話の精神 -「アカデミア タイムズ」に着目して |
33(2) |
| 奥山 尊代 | 鎌倉アカデミア、卒業生へのアンケートに見る学園の条件 -『鎌倉近代史資料 第十二集』をめぐって |
33(2) |
| 奥山 尊代 | <研究ノート>茨木のり子の詩と資質 -三篇の詩と学生たちの省察を手がかりとして- |
31(2) |
| 奥山 尊代 | 会津八一における独学 -その「文学者の修行」を手がかりにして- |
22(1) |
| 奥山 尊代 | 吉野英雄と鎌倉アカデミア-歌を通しての人間形成 | 17(1) |
| 奥山 尊代 | 鎌倉アカデミアの教育に関する一考察 -教育を支える人間の結びつきの問題を中心として- |
13 |
| 奥山 尊代 | 労働と教育-シモーヌ・ヴェイユにおける- | 10(2) |